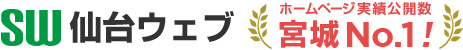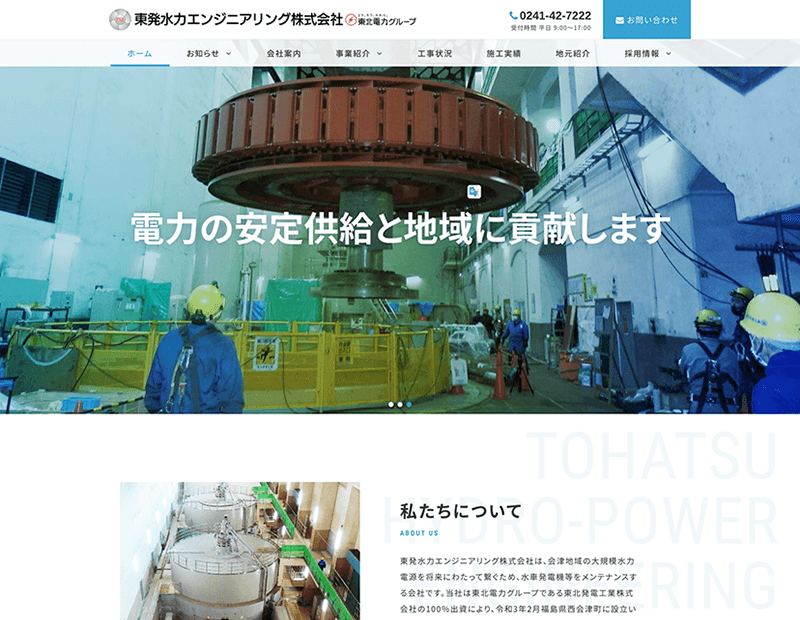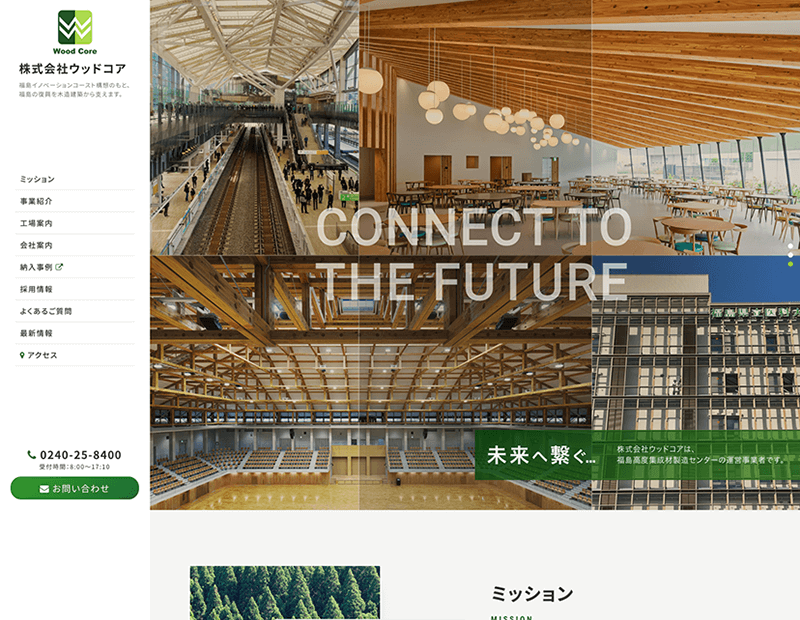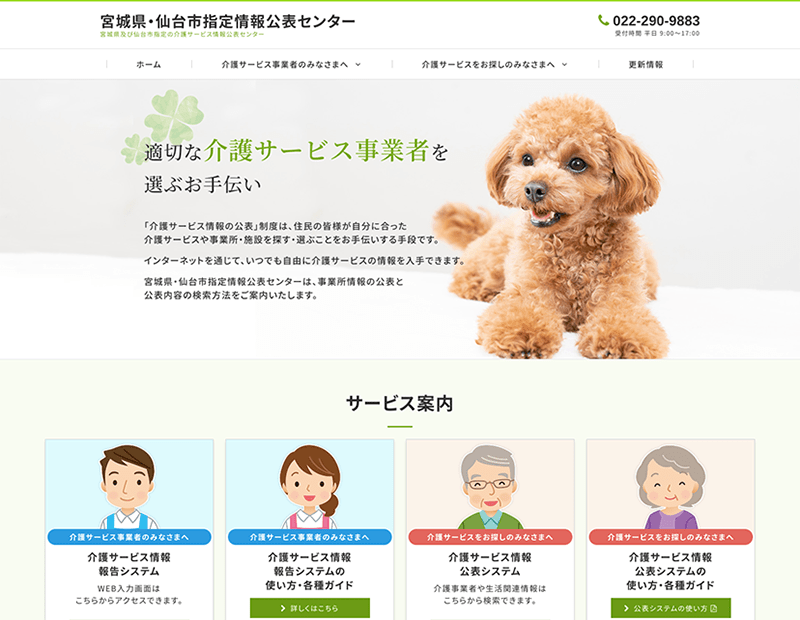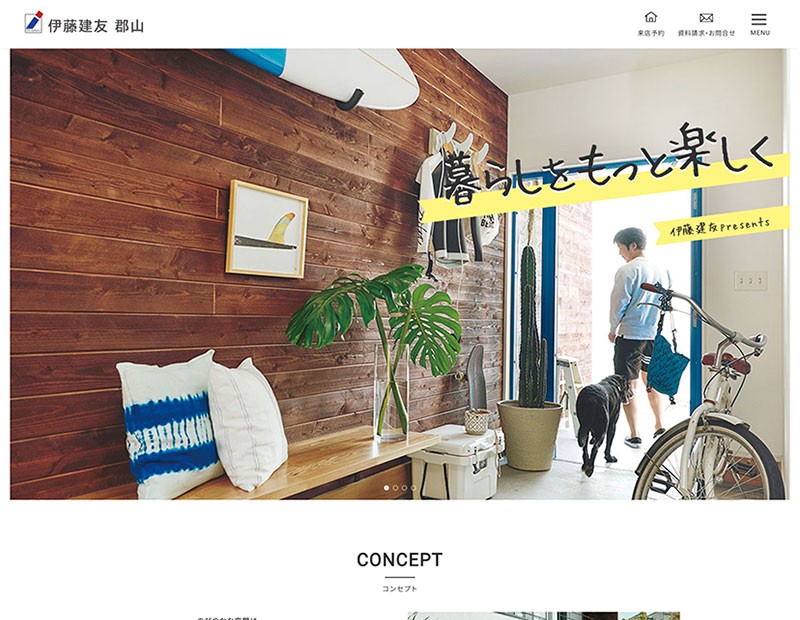よく耳にするフレーズであり、だれもが知っているようで実はよく知らないのが杜の都・仙台。
仙台は、いつごろから、なぜ杜の都と呼ばれるようになったのでしょうか。
仙台が杜の都と呼ばれているわけ
仙台は「杜の都」と言われていますが、この緑豊かなまちの姿の原点は、今から約400 年前までさかのぼります。仙台市史によれば、戦災前の仙台市街は、伊達政宗公が慶長6(1601)年に創設した城下町の遺構が、おおむねそのまま保たれていたといいます。城下町完成時の戸数は、町屋敷約1,400戸、侍屋敷約8,900戸、総数10,300戸余り。その屋敷割は、最小の町人屋敷が1戸当たり150坪(約495m2)、並足軽が175坪(約578m2)とたいへん広いものでした。城下の大部分を占める武家屋敷は、禄高のランクに応じて千坪単位まであり、ゆとりのある邸内には屋敷内の生活や産業振興に役立つ樹木の植樹が義務づけられ、果樹や生活用品の材料にもなるスギ、ケヤキ、タケなどが盛んに植えられていました。
さらにこの城下町の北・西・南の三方を囲む丘陵地帯の原生林と一体となったため、仙台は圧倒的に緑が多く、まるで緑の中に家屋敷の屋根が浮き沈みするような景観を呈していたといいます。これが「杜の都」と呼ばれるようになった由来であるというのが最も有力な説です。
仙台を「森の都」と呼ぶようになったのは明治時代後期のころからで、明治42年には仙台の観光案内書に記されています。「杜」の字を当てて書き記すようになったのはさらに遅れて第二次世界大戦後間もないころからだとみられ、また「杜」の字は「社(やしろ)」から発生したものともいわれます。
昭和45年に仙台市が「公害市民憲章」を制定したのを機に、仙台を指す場合は「杜の都」が公式表記と定められました。「杜の都・仙台」の「杜」は、山の森林を中心とする緑だけではなく、屋敷や寺社を囲む緑、人々が長い年月をかけて育ててきた豊かな緑のことです。
現代の「杜の都・仙台」の顔
第二次世界大戦時の仙台空襲で、まちの緑は焼けてなくなってしまいますが、その後の復興により「杜の都」を代表する緑は、青葉通や定禅寺通などの街路樹、青葉山公園や西公園などに代わってきました。
定禅寺通の由来は、その名のとおり「定禅寺」という真言宗の寺があったからで、かつてこの界隈は門前町でした。今はその姿を見ることができませんが、定禅寺は仙台藩祖伊達政宗公が仙台開府のとき、鬼門封じのために現在の勾当台公園のところに建立した寺で、明治時代に入り仙台藩からの保護を失うとともに廃寺(明治6年)となりました。
仙台は城下町であったため、多くの人は(仙台市民でさえ)この道が藩政時代から変わっていないのではと思いがちです。
しかし、その歴史は意外にも新しく、昭和21年の戦災復興計画の一環として整備されたもので、並木のトンネルを形成するまでに成長した定禅寺通のケヤキは、昭和33年に植えられました。幅員46m、延長0.8km、中央部の幅12mの緑地帯には遊歩道が設けられています。緑地帯と歩道の両側に植えられたケヤキは166本、高さ約16mに達しています。仙台を訪れた観光客の多くは、この通りの中央、樹木に覆われた緑のトンネル状の遊歩道をゆっくり散歩しながら杜の都・仙台の風情を全身で味わい、自分は今、間違いなく仙台に身を置いているのだと実感することでしょう。